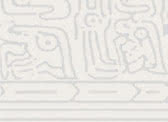四念処経講話 第二版(新修)
第四章 心念処を観ずる(二)
原文:また心に上ある者は、心に上あることを知る。
釈:もし現時点で心の量が最上ではなく、さらに増上すべきであるならば、自らの心がまだ増上すべき段階にあることを知らなければならない。
自らの心がどの段階・位地にあるか、どのような心の量か、煩悩はどうか、定力や慧力はどうか、発心は広大かそれとも狭小かを観察する。自心を振り返って観察し、仏法修行における心の状態が最大かそうでないか、最高かそうでないかを観るのである。例えば、ある者が「私は某某の衆生のために奉仕する」と発心した場合、この発心は「有上」であろうか。それは非常に低い発心であるため、まだ「上」があり、さらに増長すべきである。あるいは「私はただ生死を解脱すれば満足だ」と発心したり、「我見を断ち、三悪道に堕ちなければそれでよい」と発心する場合、この発心は「有上」であろうか。まだ「上」があり、高いものではない。
最高の発心とは何か。仏の阿耨多羅三藐三菩提(無上正等正覚)を成就しようとする発心が最高である。ある者の目標が「人天善法を修め、命終して天に生まれて楽しみを享受すればよい」というものであれば、これは小心であり、心にまだ「上」がある。また「明心見性できればよい」「十地の菩薩になれればよい」と発心するなら、これもまだ「上」がある。仏に成る発心こそが無上である。仏の発心とは何か。無量無辺の衆生を広く度し、皆が究竟の大解脱を得させるという発心が無上である。仏に成った時、仏は無上正等正覚と呼ばれる。仏の心はすべて無上の心である。
では凡夫衆生の心はどうか。すべて「有上」である。たとえ広大な発心をしても、時として心は広大でなく、すべて「有上」である。時として心念が正しくなかったり、小さくなったりする。自分個人や小さな集団、あるいはやや大きな集団のためだけの心である。この心は広大でなく、すべて「上」がある。自らの発心を観察せよ。それは「有上」か「無上」か。
刻一刻と「知」を持つこと。この「知」とは警戒心、自らを戒める心である。自心が今どの状態にあるかを内省する。これは意識の証自証分である。自ら自心を観察することを証自証分と呼ぶ。実はここにもう一つの心、すなわち意根も同時に発心しなければならない。よって観心には、意識が意根の心を観察すること、および意根が自らを内省することも含まれるが、これは非常に観察しにくい。意根は隠微であるため、観心は必ずしも意識の証自証分だけではなく、意識の自証分や意根の証自証分も含まれる。自証分とは識心が発見した事実を証明することである。発見された事実に意根の心がある場合、それを「意根がどのような心であるかを証得する」という。意根が貪りの心か瞋りの心か愚痴の心かを発見することを自証分と呼ぶ。もし意識自身や意根が自らの心を発見するなら、それは自らを内省する、自心を反照することで、証自証分である。よって証自証分は必ず自らを証明するものである。
第八識の証自証分は、第八識が自らの心行および運行の行相を発見し、証得することである。意根の証自証分は、意根が自らの心行と運行の行相を発見し、証明することである。前五識も同様で、眼識の証自証分は眼識が自らの活動を証明できることである。識心が他の識を観ることは反照とは呼ばない。あたかもこの人が他人を観察するようなもので、反照とは呼ばず、自らを発見することを反照、他者を発見することを観と呼ぶ。
修行する者の中には自らを修めず、専ら他人を修め他人を観る者がいる。自らを内省しようとしない。修行はまず自らを内省することから始まる。自らを内省する能力が備わって初めて、他者を照らし観ることができる。他者を観るとき、再び自らに光を返して照らし、対照検査し、他者を通じて自らの不足を発見する。これが警戒心、覚りの心である。よってこの「知」は、智慧のない者、禅定のない者には決して持てない。彼らの心は毎日散乱しており、散乱した心はあちこちに攀縁し、決して内省せず、心を自らに戻そうとしない。自らの心念に戻らないため、覚りがないのである。
縁に随い攀縁するのは散乱心であり、自心に対して「知」を持つことはできない。自心を知らなければ道を修めることも、覚ることも、自心を変えることもできない。よって真に修行する者は、心に刻一刻と「知」を帯びていなければならない。自らを知る明らかさ(自知之明)を持ち、さらに他者を知る明らかさ(知人之明)も持つ。菩薩は自らを知るだけでなく、他者をも知らなければならない。自己修行の段階にある者はまず自らを知り、能力が備わってから他者を知る。他者を知った後、他者を変え導くことができる。これが大乗菩薩の心である。
原文:また心に上なき者は、心に上なきことを知る。
釈:自らの心が広大無上となったならば、自らの心が広大無上であることを知らなければならない。
仏がわれわれに心の無上を観じるよう求められるが、この心の無上とは何を指すのか。それは自らの過去と比較して、過去の心はどれも今の心ほど高くはなかったということである。凡夫の心が無上である時とは、発心が非常に広大な時である。発心が広大でも行為は必ずしも広大ではないが、心は既に大きい。ただし常に大きいわけではない。観心する時、自心が何を生じ、何を変え、どの程度変わったかを、自らが刻一刻と了知しなければならない。光を返して照らす能力を持つこと、これが覚性があるということである。
自らの心が法喜に満ちているか、心量が非常に広く大きいかを観察する。仏法を修学し、今や大いなる心を発した。心は非常に精進し、必ず精進修行して早期に成就し、無量無辺の衆生を広く利益しようと誓願する。これが仏に成ろうとする広大な心を発したのであり、この時の心を無上の心と呼ぶ。しかし凡夫はこの無上を常に保つことはできない。よって自らの心念を検査し、刻一刻と光を返して照らし、心が無上であると発見したらそれを保ち、心に上があると発見したら、速やかに自らを高め、自らを覚らせ、大いなる心、無上の心を発するよう自らを促すのである。
原文:また心に定ある者は、心に定あることを知る。
釈:心の定と心の集中はやや似ており、どちらも一処に定まること、一処に集中することを表すが、それらにはなおいくつかの違いがある。集中とは、心があちこちに攀縁散乱していた状態から、次第に一ヶ所にまとまることである。心の定は単なる集中ではなく、深みがある。心が入り込んで動かず、一処に定まる。心が二ヶ所にあるのは定か。ある者は注意力が非常に強く、精力が非常に旺盛で、三ヶ所に定まっても専注力が相当に強く、どこもよく配慮できる。大智慧大禅定の者でなければこのようにはできない。
智慧も禅定もない者は、心を一処に定めることすらできず、一つのことも円満に成し遂げられない。大智慧の者は千軍万馬を指揮しても、依然として泰然自若として余裕がある。心が二ヶ所三ヶ所に定まるのは定か。ある者は四ヶ所に定まっても、やはり定である。その心念の力がどうか、各所で精力が非常に旺盛か、すべて配慮しきれるか、了別が明瞭か、思惟力が敏捷かによる。定とは何か。一つの法に専注することを定といい、二つの法に専注することも定という。この人は能力が高く、同時に十人全員を見張れる。能力の低い者は一人を見張ることもできない。定とは何か。問題を解決する能力と精力、これを定という。心が非常に散乱している者は心力が弱く、この時は心を集中させる訓練しかできず、定めることはできない。定力が相当に良い者だけが、心を幾つかの箇所に定めて散乱しないよう訓練できる。
仏がここで二つの現象――心の集中と心の定――を挙げられたのはなぜか。両者にはどのような違いがあるのか。集中には深みがなく、力がない。ただ散乱していないだけである。定には一定の深みがあり、必ずしも一処に集中しているわけではない。能力の高い者は一軍を統率し、軍長や司令官となれる。能力の低い者は班長にしかなれない。これが心の差、能力の差である。
定にはもう一つの概念がある。広義では決定心を指す。心がある種の法に対して決定的な心を生じ、認め肯定することである。例えば仏法を修学し、十信位に至った時、仏法に対して決定心を生じ、必ず菩薩となって自利利他すると決める。これが決定心である。その後、菩薩の六度に対して決定心を生じ、必ず菩薩の六度を修学し、必ず明心見性しようと誓願する。これも決定心である。あるいはまた決定心を生じ、五蘊十八界が無我であると観行し、我見を断とうとする。これも決定心である。決定心には二種類ある。一つは意識心の決定、もう一つは意根の決定である。最初に決定を起こすのは意識で、最終的に決定を起こすのは意根である。そうして初めて実行に移せる。意識が決定した後、意根に報告して審査を求め、意根も決定すれば、この時初めて意識の決定は有効となる。結局は意根が決定するのである。
いかなる法の決定も、実行する時は意根が決定する。意根が決定して初めて六識は行動を起こせる。六識の決定は行動に移せない。六識は五陰身の主人ではないため、主導権がなく、身口意の行いが自在でない。身口意の行いは意根が発動する。意根は指導者であり、意識は参謀に過ぎない。指導者は参謀の意見を採用することも不採用とすることもできる。採用すればあたかも意識が主導しているように見えるが、実際には依然として意根が主導している。仏法においても世俗法においても、もし意根が主導して決定すれば、すべての精力、注意力が完全に向けられ、六識は専心して決定を実行する。結果と過程は六識の智慧を示すだけでなく、意根の智慧も含まれ、如来蔵が智慧の種子を蔵する。
定は六識と七識の両方が持ちうるが、定の実質は依然として意根の定である。意根の定が六識の定を決定する。意根に定がなければ、六識にも定はない。六識と七識はどちらも発心できる。一つは表層、もう一つは深層である。最終的には意根の発心が根本となり最後の選択となる。意根が発心して初めて行動力が生まれる。心の広大と狭小も、意識と意根の広大と狭小に分けられる。
原文:また心に解脱ある者は、心に解脱あることを知る。
釈:自らの心が解脱した時、自らの心が解脱したことを了知すべきである。
観心する時、自らがある法から解脱したならば、自心がその法から解脱したことを知るべきである。解脱とは何か。一本の縄で結び目を固く縛られ、自由自在でなく自由がない状態が不解脱である。逆に結び目を解き、自由自在で束縛されない状態が解脱である。縄の結び目は心の結び目(心結)に喩えられる。なぜ心結が生じるのか。心がある法に繋がれ、離れられず離脱できない状態が結縛、またの名を係縛という。心をその法から移し離脱させ、再び気にかけず心に留めなければ、結び目は解ける。これを解脱という。衆生の心結は極めて多く、一つの法に触れるごとにその法に粘着し、一つの法に束縛され、心に一つの結び目が増える。衆生は境に執着する習慣が非常に強く、境に対して無心になることができず、たとえ束縛されて苦しくても覚ることができず、解脱する方法を知らない。
心結は無量無辺に多く、大小さまざまである。衆生の心はどの法に係縛されているのか。色受想行識の五陰、六根と六塵の十二処、六根六塵六識の十八界、我、人、衆生、寿命、三界世間の一切の法の上に、すべて結縛がある。凡夫は一つの結び目も解かず、心は解脱しない。色を見れば色に縛られ、心は色から解脱しない。声を聞けば声に縛られ、心は声から解脱しない。香を嗅げば香に縛られ、心は香から解脱しない。味を嘗めれば味に縛られ、心は味から解脱しない。触を覚れば触に縛られ、心は触から解脱しない。法を知れば法に縛られ、心は法から解脱しない。
では解脱とはどのような境界か。色を見る時に色に執着せず、心念を動かさず、貪らず厭わず、苦しまず楽しまない。これが心解脱の相貌である。色が来たり去ったりしても、憂いも喜びもなく、全く掛礙がない。心は解脱している。声・香・味・触・法が来たり去ったりしても、憂いも喜びもなく、全く掛礙がない。心は解脱している。人・事・物・理が来来去去しても、憂いも喜びもなく、全く掛礙がない。心は解脱している。私たちは解脱の味を嘗めたことがあるか。全体的には、解脱の味を嘗めたことはない。個々の法について時々心で理解できて、一時的に解脱することはある。例えば以前はあることに非常に執着していたが、思惟分析を通じて、このことに執着しても無駄だと感じ、そのためこのことについては手放して執着しなくなった。これをあることについて心が解脱したという。時には衣食住に対してやや諦観し、心が少し解脱することもある。
また例えば受陰の機能作用に執着しなくなった場合、享受しても享受しなくても、気持ちが良くても悪くても、すべてどうでもよく、好きでも厭わずでもない。受覚に係縛されず、受に執着しなければ、受陰の上で解脱したのである。最も解脱しにくいのは識陰である。必ず何らかの法を知って初めて、心が面白く退屈しないと感じ、知らないと非常に苦しく感じる。修行を通じて識陰の作用への執着が減り、ある人・事・理について無理に知ろうとしなくなり、何も知らない時も心が退屈に思わなければ、いくらか解脱したのである。もし色を見て声を聞く上で心が執着せず、喜びも厭いも生じず、来ても去ってもどうでもよければ、心は解脱したのである。五蘊十八界に心が執着せず、欣喜せず貪着しなければ、心は解脱したが、これはまだ究竟の解脱ではない。究竟の解脱は仏地の解脱である。
原文:また心に解脱なき者は、心に解脱なきことを知る。
釈:もし心がまだ解脱していなければ、自らの心がまだ解脱していないことを了知しなければならない。
観心の中で、自らがある法に対して心がまだ粘着しており、解脱していないと発見したなら、自らがはっきりと了知しなければならない。これには時々自らに光を返して照らし、あることに出会った時、自心がどのような状態か、このことに対して非常に貪り執着して離れられず、心が葛藤し苦悩しているか、あるいはまた心喜び楽しんでいるかを内省する。もしそうであれば、心がこのことによって係縛されている証拠であり、解脱しておらず、心で知らなければならない。
例えば他人が私にいくら借りがあるか、私が刻一刻とこのことを念じていれば、私の心はこのことによって係縛されており、解脱していない。人や事柄に対して心が常に念じ想うのは、心が係縛されている証拠であり、解脱していないのである。解脱を得られない心は苦悩し自在でなく、楽しみもまた煩悩で自在でない。特に楽しいことはなおさら煩悩である。心が平穏で波風立たなければ、それは解脱した自在であり、最も心地よい。苦受自体が苦であり、楽受は壊苦(壊れる苦)である。不苦不楽受は行苦(変化する苦)である。すべての受は苦である。一切の法に執着しなければ解脱である。
観心する時、いかなることに出会っても、いつでもどこでも自心を観察し、心が法に対して解脱しているかどうかを検査し、心で刻一刻と了知しなければならない。もし法に対して非常に強い瞋りや強い喜愛を生じ、心が境に粘滞すれば、解脱していない。心念がある限り、それは束縛であり、解脱していない。修行の目標は心に解脱を得させることであり、しかも最も究竟なる解脱、仏地の大解脱を得させることである。そのためには一切の法に執着してはならない。
真の解脱には二つある。一つは人我執を断じ、五蘊十八界に執着せず解脱を得ること。これは三果・四果の聖者である。もう一つは法我執を断じ、一切の法に執着せず解脱を得ること。これは初地・二地・三地・四地……十地・等覚の菩薩である。法執を断じ尽くし、一切の法に全く執着しなければ、それが仏である。一切の法に対して、すべて解脱自在であるのは仏ただお一人である。菩薩は一切の法の上で、一部は解脱しているが、一部は解脱していない。心が執着すればするほど、頑固であればあるほど、解脱しない。凡夫衆生はすべて五陰十八界や三界の世俗法に執着している。ある法はまだ執着できず、その煩悩はまだ現前しないため、法執を断じられない。法執は必ず地上の菩薩から断ち始める。
以上、観心の内容について述べた。自心に貪瞋痴の煩悩があるかどうか、普段ある人・事・物・理、一切の法に対して貪りの念か離貪の念か、瞋りか否か、痴か否か、心念が集中しているか散乱しているか、心行が広大か狭小か、発した心が有上か無上か、心に定があるかないか、解脱しているかいないか。これらの内容が観心の範囲である。
毎日自らの心念をありのままに観察できれば、心は非常に細やかになり、禅定は増強される。心の状態を観察できさえすれば、それは賊を認識し見張るのと同じで、まず賊を認識し、次に賊を見張る。最後に賊は何も働きかけられなくなり、自ら去って家財は盗まれずに保たれる。毎日このように観心し、心には常に「知」がなければならない。この「知」が覚りの心である。どれほどの人が覚っているか。多くはない。多くの者は六塵の境界に随って転じ、甲が来れば甲に従い、乙が来れば乙に去り、丙が来れば丙に走る。東西南北四維上下、縁のある所へどこへでも行く。衆生の心はこのように散乱し、攀縁し、解脱せず、あらゆる境界に執着し係縛されている。修行とはまず心を認識し、次に心を見守り、最後に善し悪しを知ることである。心は徐々に変わり、万法を空と見透せば、解脱を得るのである。
原文:かくの如く、あるいは内の心に於て心を観じて住し、また外の心に於て心を観じて住し、また内外の心に於て心を観じて住す。
釈:このように観行する。心はあるいは内心を観じることに住し、その後は外心を観じることに住し、最後に心は内外の心を同時に観行することに住する。
観心する時は、内に向かって色身を縁とする内心を観行し、過去未来を縁とする内心を観行し、思惟・推理・判断・研究・反省する内心を観行する。心は内心を観じることに住し、また六塵境界を縁とする外心を観じ、心は外心を観じることに住する。そして同時に内外の心を観じ、心は内外の心を観じることに住する。観行する時、内外の心の状態をすべて観行しなければならない。自心が今まさに動いている念で外の六塵境界に接触しない心が、貪りか瞋りか愚痴かをすべて明らかに観察する。この心が有上か無上か、解脱しているかいないかをすべて観察しなければならない。これを成し遂げるのは容易ではない。自らを知る明らかさ(自知之明)は容易に持てないため、自心を観じることは容易ではない。各人の内心の結縛がそれほど多いのに、自心を観じられなければ問題を発見できず、自心を変えることもできない。自心がどの状態にあるか、善か悪かさえ発見できなければ、どうやって変えようか。
『楞厳経』で仏は七識心が色身の内にも外にも、また色身の中間にもないと説かれるが、仏が観心について説かれる時、なぜ内心と外心があると言われるのか。心念が色身の内にある場合、便宜上内心と呼ぶ。心が外に向かって六塵境界に攀縁する時、あたかも外に出たように見えるが、実際には出ていない。これはただの方便の説法である。あたかも外界に攀縁しているように見えるため、外心と呼ぶ。外心は六識が外に攀縁する時の名称である。
観心する時、もし心が回想していると発見すれば、これは独頭意識が作動しているのである。次に心を再び内に収め、この心がどのような心理状態にあるか――貪瞋痴があるかないか、解脱しているかいないか――を振り返って観る。次に心が六塵境界に対する時、貪瞋痴があるかないか、定があるかないか、解脱しているかいないか、有上か無上かを観る。
自らの心理状態を観察すれば、自心が清浄かどうかが分かり、自らの心念が善か不善か、思想が正しいか間違っているかが分かり、どう処理すべきかが分かる。ではどう処理すべきか。意根は意識が観察した状況を知り、後で思量する。何を取るか捨てるかは意根次第である。意識は一定の思惟作用を起こせるが、残りはすべて意根の仕事である。意根が思量した後、選択を採り、選択の結果は少しずつ良くなり、以前の貪瞋痴の煩悩を少しずつ改める。意根が変わる前提は、意識が善く思惟し、何が正しく何が正しくないかを知り、思惟の過程と結果を意根に伝えることである。意根は思量した後で理解し、以後は正しく選択し決定する。こうして意根は降伏され変わるのである。
意識と意根の二つの心は働く時に分業があり、それぞれ重点を置き、和合して運作し五陰身の身口意行を完成させる。修行はまず意識が正念正見を持ち、意識が理を明らかにし、意識が智慧を持たなければならない。次に意根が意識に依り、自らの思量を起こして初めて理を明らかにし、智慧を生じ、選択決定心を生じて自心を変える。心はこのように変わるのである。自らを変えるにせよ、環境を変えるにせよ、一切の法を変えるにせよ、すべてこのように変わり、意根が主導して選択し、如来蔵が随順して変わるのである。
意根が思量して明らかになり、選択心があれば何とかなる。意根が比較的堅固で力があれば何とかなる。「私はどうしてもこうする」と決めれば、如来蔵は仕方なく、そうさせるのである。真に力があるのはもちろん如来蔵であり、何ものも如来蔵が意根の決定を実施するのを阻めない。ただしその後には因縁や業種などの条件が必要である。業種には前世の業種と現存の業種がある。現存の業種が作用しようとするなら、種子の力が相当に相当に大きくならなければ、業種は直ちに成熟して現行できない。意根が成し遂げたいことは成し遂げられる。もし意根に力がなければ、蔵する業種は微々たるもので力がなく、因縁は成熟しにくい。意根が力を持つほど、蔵する種子はより充実し、成熟はより速く、すぐに果報を実現できる。
もし意根に力を持たせたいなら、さらに智慧が必要である。智慧には禅定が必要である。智慧が大きいほど、より良い業種・善業種を蔵し、一生の修行で成就し、一つのことを成し遂げるのも速い。もし心に力を持たせたいなら、定が強く、慧も強くなければならない。決定性が非常に強く、意志が堅固である。決定性が強くないと業種は成熟しない。例えば念仏する時、心はただひたすら極楽世界に往生しようと、非常に堅固であれば、極楽世界のあちらで蓮華が造り変えられ、極楽世界の景象も現前する。どうやって現前するのか。意根が非常に極楽世界を念じれば、如来蔵は極楽世界を現出させる。意根が念じなければ現前しない。
修行はまず意識が前行を導き、しかも正しく導き、一つの正しい道を開拓する。そうして初めて意根が後に随行でき、如来蔵が意根に随って一切の法を出生し、一切の法を成就できる。もし意識が道を誤って導けば、意根も道を誤って随い、如来蔵は東西を弁別せず、意根に随って染汚法を出生し、結果は生死輪廻の苦である。三能変識(第八識・第七識・第六識)の中で、意識はこのような作用を起こし、意根はあのような作用を起こし、第八識は別の作用を起こす。それぞれに役割がある。仏に成る道をどう歩むか、どう仏に成るか、心は明らかにすべきである。意識が広く学び多く聞き、正しい道を選択し、意根を導く。意根が決定心を生じれば光明の大道を歩み、心が変わり修行は成就する。
世俗法もこのように成就する。意識が道を導き、意根が後に随い、如来蔵は後備軍で、糧秣を十分に提供し、何を求めても提供する。最後に成就できる。例えば家を建てる場合、意根と六識が上で家を建て、如来蔵が背後で材料を提供する。八つの識が協力すれば、家は造られる。如来蔵が意根に協力する前提条件は、六識と七識がまず協力し、六識が導き、意根が思量した後「私はどう家を建てるか、どんな様式で建てるか」と決定する。如来蔵は随順して共に建造する。三能変識は一つでも欠けてはならない。誰が最も重要か。皆重要であるが、もちろん後の方ほど重要である。
六識と七識が前方で道を開拓し決定する。後方の如来蔵が原材料を与えず、種子を提供しなければ、六識と七識もどうしようもない。原材料はどこから来るのか。やはり六識と七識が共に蔵したものである。如来蔵は無から有を生じない。種子を蔵していなければ種子を取り出せず、原材料は供給できない。六識と七識がまず資糧を蔵し、五識も参与する。資糧を蔵した後、事を成そうとする時、因縁が具足すれば如来蔵が再び取り出す。よって私たちが大いなる心と大いなる願を発して何らかの法を成就しようとするなら、まず種子を蔵さなければならない。そうでなければ何の法も成就できない。福を修めずに仏に成ろうとしても、それは方法がない。如来蔵は虚無から種子を生じられず、巧婦も米無しでは炊事が難しい。よって一切の法の造作は、やはり自らが造作するのである。種子は如来蔵の庫裏に置く。他の生滅する頼りない所には置けない。使う時に初めていつでもどこでも取り出せる。取り出せなければ、妄想しても無駄である。修行はやはり六識と七識が自ら修め、六識と七識が修まり、六識と七識が変われば、万法は変わり、六識と七識の願いを満たす。これが修行の過程である。
原文:あるいは心に於て生法を観じて住し、あるいは心に於て滅法を観じて住し、また心に於て生滅法を観じて住す。
釈:観心する時、心の上の生法を観察し、心は生法を観察することに住する。あるいは心の上の滅法を観察し、その後心は心の滅法を観察することに住する。最後に同時に心の生法と滅法を観察し、心は生滅法を観察することに住する。
生法とは何か。私が今一つの問題を思考し、突然一つの念が現れ、何らかの問題を考えようとする。問題を考えるという法が生じる。新たに生じた法とは、例えばちょうど一つの心念が起きた時、あるいは目がちょうど色を見て心が生じて運作する時である。これを生法という。心に善に向かう心行が現れたり、ある貪りの念が出たりする。これを生法という。今瞋りの心が生じた。これを生法という。今心に定がある、心の定という法が現れた。今ある事・人・物について諦観でき、解脱の法が現れた。これを生法という。元々なかったが今現れたのが生法である。
滅法とは既にある法が消えて見えなくなることである。例えば以前の貪りの念が今はない、これが滅法である。以前心が散乱していたが今心が定まり、散乱心が滅した、これが滅法である。さっきまで怒っていたが今は怒っていない、瞋りの心が滅した、これが滅法である。自らの心念の生住異滅、心の状態をすべて掌握し、自らを理解した後、自らがどのような心行かが分かる。禅定・智慧・持戒、戒定慧が具足し無我を証得する時、心念が転変し、大智慧が生じる。徐々に貪瞋痴の煩悩を断除できる。これは自然の修行過程である。例えば目の前に一匹の猿がいる。あなたがそれを見張れば、徐々にそれも居心地が悪くなり、動かず走らず跳ねない。ただそれを認識し、見張ればよいのである。あたかも窃盗犯のように、まずその顔を知り、認識し、見張る。そうすれば彼は手足を動かせず、人に見張られては盗みを働きにくい。自らの心はまるで泥棒のようである。それを認識し、見張れば、後の仕事は何とかなる。
心の中でこの法が生じ、あの法が滅する。同時にすべて観察しなければならない。この時定も増強され、慧も増強される。初めは生を観じ、後には滅を観じ、さらに後には生滅を同時に観じる。初めは内心を観じ、後には外心を観じ、さらに後には内外の心を同時に観じる。定慧が増強されて初めてできるようになる。同時にすべて観じるのは、心が一つの法に住するのか、二つの法に住するのか。三つ四つの法に住しても定である。
よって定の概念とは何か。ただ一境に専注することや心を滅することを定と呼ぶだけでなく、すべての法を明らかにする能力があれば定がある。もちろん慧もある。もし定慧がなければ、一つの法を観じても定中で観じるのではなく、この一つの法は解決できず、慧は生じない。生法・滅法・生住異滅、これら多くの法をすべて観察できれば、この定力は相当に良い。定が浅ければできない。この中にも智慧が現れ、すべての法が解決される。一切の法の出生と滅去を見張れれば、定慧が具足する。この中に戒はあるか。法にかなわない心行がなければ戒である。こうして戒定慧が具足する。毎日自らを観察できさえすれば、戒定慧が具足し、初果から四果まで成就できる。ただ覚らないことを恐れる。心が境界に随って散じ去り、覚知しないのである。このように観行した後、最終的な結果は何か。心心念念、観心する心がある。
原文:なおまた智識の成せる所、及び憶念の成せる所、皆な心の思念有らんことを会し、彼れ当に依る所無くして住すべし。且つ世間の何ものにも執著せずして住すべし。諸比丘よ、比丘はかくの如く心に於て心を観じて住す。
釈:智慧の認知によって形成されたもの、および心の憶念によって形成された結果、心念には必ず心に関する念が現れるであろう。あなた方はいかなる法にも依らずに住し、かつ世間のいかなるものにも執着せずに住すべきである。諸比丘よ、比丘はこのように心において心を観じて住すべきである。
一貫して専注して自心を観察するため、禅定と智慧が共に向上する。この時心心念念すべて自心である。これは智慧による観行の結果、憶念の結果である。心は常に自心を思念し、自心を観察し、自心を思考分析し、自心を調伏する。しかし心にこれらの念があるため、心は清浄でなく、心念から解脱できず、心念を滅し、心念を空と見、心にいかなる法もなく、いかなる法にも依らずに住すべきである。かつ世間のいかなるものにも執着せずに住すべきである。心は空空蕩蕩、清清浄浄である。
智識の成せる所とは何か。自心を観察するその心が、絶え間ない観行を通じて智慧が次第に向上し、一つは境界に随って流転せず、二つは自心の心念を明らかに観察し、三つは自心が降伏される。智慧がなければ、心は境界に随って流転し覚知しない。智慧があって初めて覚知する。これを智識という。心念を観察し続ける心を智識という。憶念とは何か。観心の後、心は一貫して自心の状態を回想思惟する。これが憶念である。観心の全過程が心の中で旋回し反復し、自心が置かれている状態を知る。これは心念が成し遂げたものであり、これも憶念と呼ばれる。観心の最終結果、心には常に「我」があり、常に自心が貪瞋痴か無貪瞋痴かを憶念回想観察し、常に自心の置かれている状態を思惟し、一貫して自心を思念する。定慧が共に具足する。
観行が堅固な心念を形成した後、観心に住する。心が何かに住すれば係縛である。最後にこの心念も放って空にし、住するところなく、心は初めて解脱を得る。観る所の心も投げ捨て、住するところなく、心は空となる。あたかも洗濯するように、衣服が洗い清められた後、石鹸の泡と水はすべて除去しなければ衣服は着用できる。観は石鹸や洗剤や水のようなものであり、衣服は観の対象である。観心の後、心心念念すべて心であり、内心は刻一刻と自心を思念する。最後に思念する念も空にしなければならない。心は住するところなく、思念に住さなければ、心は空となる。観じる心、観じられる心はすべて無常・空・幻化・執着すべきでない。観じる者と観じられる者がすべて泯滅すれば、心は空となり寂静する。観じる者と観じられる者はすべて無常であり、どちらも我ではない。この観じられるものは六塵境界ではなく、心である。観じる者は六識と七識であり、観じられる六識と七識はすべて空であり、すべて住するところなく執着してはならない。
四念住を修め終われば我見を断つ。心を空にすれば我見を断ち、かつ三果・四果を証得できる。観じる心も観じられる心も真実でないこと、生滅異住であること、すべて生滅変化し起滅無常であること、どちらも我でないことを了知する。空にした後、心は依る所なく住する。もし依る所があれば、それを真実と見做し我見を断てない。依る所なく住した後、かつ世間のいかなるものにも執着せず、心にも依らず、物にも依らず、心を空空と放ち、物も空に放つ。世間のいかなるものも心に執着しなければ、空果を証得する。内心に法が存在する限り、それを空にし、真実と認めなければ、我見・我執を断てる。
大乗法の観点から言えば、一切の法を空にした後、ただ一つの如来蔵が空でなく存在する。これは大乗法の如来蔵を証得した境界である。あたかも『楞厳経』で説かれる耳根円通のようである。観じる者も観じられる者も空にし、空も空にし、すべての空を空にする。耳根円通を修め終われば、ただ一つの如来蔵が残る。『円覚経』もこう説く。心に心念がある限りすべて空にすべきであり、空の心念もまた空にすべきである。空にできる者と空にされる者をすべて空にし、如来蔵を除いて何も存在しなくなる。その後如来蔵にも執着しなければ、修行は頂点に達する。無量千万億の化身が現れる。修め終われば甚深の禅定と智慧の三昧境界である。
修行はこのように一路空にし続け、凡そ生滅変化する法をすべて空にし、その後何らかの法が空であると考えるなら、またこの知見も空にし、法を空にした後、またこの空も空にし、心中に物がある限りすべて空にし、心も空にし、心中の物も空にし、空にできる者と空にされる者をすべて空にする。ただ一つどうしても空にできない如来蔵が残れば、究竟して頂点に達する。これは一般的な明心見性ではなく、究竟して頂点に達した明心見性である。観音菩薩が修める耳根円通章はこのようである。四念処を修め終わっても、五蘊十八界を空にすることはできるが、必ずしも如来蔵の不空を証得できるとは限らない。