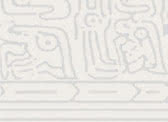阿含経十二因縁釈
第四節 四食と十二因縁の関係
(三七一)四種の食の集起
原文:その時、世尊は諸比丘に告げられた。四種の食があり、衆生を資益し、住世させ、摂受し長養する。何が四であるか。一に粗摶食、二に細触食、三に意思食、四に識食である。
釈:世尊は諸比丘に告げられた。四種の食があり、衆生の生命体を滋養し助益し、衆生が資助され增益され、世間に住し、摂受され滋養されることを可能にする。その四種とは何か。第一の粗摶食は比較的粗雑な四大から成る飲食であり、色身を滋養し生命を維持する。第二の細触食は比較的微細な触食であり、六根が六塵に触れること、および六根・六識・六塵の三者和合による触れを食とし、五受陰を滋養し生命を維持する。第三の意思食は意識と意根の思量を食とし、五蘊身を滋養し生命を維持する。第四の識食は識心の持身作用を食とし、五蘊身の運行を維持し生命を保つ。
第一の粗摶食は欲界の人間衆生と畜生が摂取する食物であり、咀嚼により腸胃に入り身体に吸収され、色身を滋養し生命を維持して世に住させる。人間と畜生の色身は四大から成る粗重な色身であるため、粗雑な飲食で維持する必要がある。微細な色身は微細な飲食で維持するか、あるいは禅定で維持する。四大色身がなければ四大から成る飲食は不要であり、禅定のみで生命を維持できる。欲界の天人は四大から成る飲食を摂るが、その飲食は非常に微細であり、咀嚼せず鼻で香りを嗅ぐだけで満足する。
第二の細触食は、根と塵が互いに触れることを食とする。四大色身を持つ衆生は触食を必要とし、四大色身を持たない衆生も触食を必要とする。なぜなら無色界の衆生は四大色身を持たないが意根があり、意根が法塵に触れることで無色界衆生の生命を維持するからである。なぜ衆生は触食を必要とするのか。衆生には色蘊・受蘊・想蘊・行蘊・識蘊があり、六根・六塵・六識がある。根と塵が触れて六識が生起するときのみ五蘊は運行し、六塵の境界を了別し、六塵の境界を持つことができ、これが生命に必要不可欠である。もし触食がなくなれば、衆生は必ず涅槃に入り、生命は消滅する。
第三の意思食は、主に意根が法を思量する食を中心とし、意根は恒に審査思量して一瞬も休まず、意識は断続的に思量する食を補助とする。思量があるからこそ五蘊は運行し続け、塵境を取り入れることができ、これは三界の無明衆生に必要不可欠である。もし思食がなければ、衆生は必ず涅槃に入り、生命は消滅する。
第四の識食は、八つの識を食とし、生命の運行を維持する。八識にはすべて持身の作用があり、第八識は絶対的な持身識であり第一の持身識、七識は相対的な持身識であり第七識は第二の持身識、意識は第三の持身識、五識は第四の持身識である。第八識と第七識の二識が共同で持身すれば、五蘊生命体は世に住することができるが、五蘊の機能作用は完全ではなく、ほとんどの衆生は意識の持身作用および五識の持身作用を離れることができず、五蘊の機能が円満に運行して初めて生命は相続し集起する。ただし、諸根互用の八地以上の菩薩は除かれる。第八識には絶対的な持身作用があり、あらゆる食の根源と基礎であり根本食であるが、ここでの識食はやはり六・七識の食を主とする。
衆生が必要とする四種の食は、すべて識食から離れることができず、識食を根本食として五蘊身を摂受する。これを基礎として初めて触食と思食が必要となる。甚深な禅定がなければ、地水火風の四大種子から成る摶食を色身の栄養素としなければならない。禅定が比較的深ければ、摶食を断除し、識食と思食を主として色身を滋養し、軽微な触食を持つことも、一部の触食を断除することもできる。衆生がこの四種の食に依存すればするほど、生死は流転し、苦受は増す。禅定が深まれば深まるほど、この四種の食への依存は減り、生命は自在となるが、第八識への依存は永遠に断除できず、第八識を執着しなければよい。
原文:この四食は何を因とし何によって集起するか。何によって生じ何によって触発されるか。すなわちこれらの諸食は、愛を因とし愛によって集起し、愛によって生じ愛によって触発される。この愛は何を因とし何によって集起するか。何によって生じ何によって触発されるか。すなわち愛は受を因とし受によって集起し、受によって生じ受によって触発される。この受は何を因とし何によって集起するか。何によって生じ何によって触発されるか。すなわち受は触を因とし触によって集起し、触によって生じ触によって触発される。
釈:この四種の食はどの法を因として現れるか。どの法の集起によって引き起こされるか。どの法の出生によって生じるか。どの法の触発によって引き出されるか。この四種の食は愛を因として現れ、愛の集起によって引き起こされ、愛の出生によって生じ、愛の触発によって引き出される。ではこの愛はどの法を因として現れるか。どの法の集起によって引き起こされるか。どの法の出生によって生じるか。どの法の触発によって生み出されるか。
この愛は受を因として現れ、受の集起によって引き起こされ、受の出生によって引き出され、受の触発によって生み出される。この受はどの法を因として現れるか。どの法の集起によって引き起こされるか。どの法の出生によって生じるか。どの法の触発によって生み出されるか。この受は六根が六塵に触れることを因として現れ、触の集起によって引き起こされ、触の出生によって生じ、六根が六塵に触れることによって引き出される。
もし愛がなければ、愛が滅尽すれば、識食は生じず、触食もなく、触食がなければ思食と摶食もなく、四種の食は滅尽して生じない。したがって貪愛は苦であり、貪愛は生死流転の苦因である。
原文:この触は何を因とし何によって集起するか。何によって生じ何によって触発されるか。すなわち触は六入処を因とし、六入処によって集起し、六入処によって生じ、六入処によって触発される。六入処の集起が触の集起であり、触の集起が受の集起であり、受の集起が愛の集起であり、愛の集起が食の集起である。食が集起するがゆえに、未来世の生老病死・憂悲悩苦が集起する。かくのごとく純大苦聚が集起する。
かくのごとく六入処が滅すれば触は滅し、触が滅すれば受は滅し、受が滅すれば愛は滅し、愛が滅すれば食は滅する。食が滅するがゆえに、未来世の生老病死・憂悲悩苦は滅する。かくのごとく純大苦聚は滅する。
釈:この触はどの法を因として現れるか。どの法の集起によって現れるか。どの法の出生によって引き出されるか。どの法の触発によって引き起こされるか。触は六入処を因として現れ、六入処の集起によって引き起こされ、六入処の出生によって生じ、六入処の触発によってもたらされる結果である。六入処の集起は触の集起であり、触の集起は受の集起であり、受の集起は愛の集起であり、愛の集起は四種の食の集起である。食が集起するがゆえに、未来世の生老病死憂悲悩苦が集起し、純大苦聚が集起する。
これらの法の相関関係によれば、もし六入処が滅すれば触は滅し、触が滅すれば受は滅し、受が滅すれば愛は滅し、愛が滅すれば四種の食は滅し、四種の食が滅すれば、未来世の生老病死憂悲悩苦純大苦聚は滅する。
(三七二)四食と十二因縁の関係
原文:その時、世尊は諸比丘に告げられた。四種の食があり、衆生を資益し、住世させ摂受長養する。何が四であるか。一に粗摶食、二に細触食、三に意思食、四に識食である。
釈:世尊は諸比丘に告げられた。四種の食があり、衆生を滋養し助益し、衆生が摂受され長く世に住することを可能にする。その四種とは何か。第一は粗雑な飲食、第二は微細な触食、第三は意識と意根の思食、第四は識心の了別食である。
原文:その時、頗求那という名の比丘が、仏の後ろにいて仏に扇ぎながら、仏に白した。世尊、誰がこの識を食とするのですか。仏は頗求那に告げられた。私は識を食とする者があるとは説かない。もし私が識を食とする者があると説くならば、あなたはそのように問うべきである。私は識が食であると説く。あなたは「何の因縁によって識食があるのか」と問うべきである。私は答えるであろう。未来の有を招き、相続して生じさせるためである、と。
釈:この時、頗求那という名の比丘が仏の後ろに立って仏に扇を扇ぎながら、仏に言った。世尊、誰が識心を食とするのですか。仏は頗求那に告げられた。私は識を食とする者があるとは説かない。もし私が識を食とする者があると説くならば、あなたはそのように問うことができる。しかし私は識心もまた衆生を資益する一つの食であると説く。あなたはこう問うべきである。何の因縁によって識心というこの食があるのか。私は答えるであろう。識食は未来世の有を招致し、三界の有を相続して絶えず生じさせるためである、と。
なぜ仏は七識八識を食とする者がないと説くのか。なぜ仏は七識八識を食とする者がないと説くのか。識食を必要とする者は五蘊の衆生であるが、五蘊の衆生は和合体であり主宰者がない。識は主宰者なき和合体の中の最も主要な要素であり、識は自らを食とせず、主宰者がいなければ食とする者もいない。なぜ識食があるのか。仏は、識食があるからこそ未来世の三界の有を感召できると説く。この言葉から、小乗と中乗の識食は六識の食を指し、六識の食があれば後世の名色があることを理解できる。一方、大乗の識食は七・八の二識を含み、七・八の二識を主とし、六識を補助とする。
原文:有があるがゆえに六入処がある。六入処を縁として触がある。頗求那がまた問うた。誰が触れるのか。仏は頗求那に告げられた。私は触れる者があるとは説かない。もし私が触れる者があると説くならば、あなたはそのように問うべきである。誰が触れるのかと。あなたはこのように問うべきである。何の因縁によって触が生じるのか。私はこのように答えるべきである。六入処を縁として触がある。
釈:三界の有があるがゆえに六入処があり、六入処を縁として触が生じる。頗求那がまた仏に問うた。誰が触れるのですか。仏は頗求那に告げられた。私は触れる者があるとは説かない。もし私が触れる者があると説くならば、あなたはそのように問うべきである。誰が触れるのかと。あなたはこのように問うべきである。何の因縁によって触が生じるのか。私は答えるべきである。六入処が触れることによって初めて触が生じる、と。
なぜ仏は触れる者がないと説くのか。なぜ受ける者、愛する者、取る者、有る者、生まれる者、老い死ぬ者がないのか。触とは根と塵が触れることであり、内六入と外六入の触れである。根と塵、内外の六入には自性がなく、主宰がなく、主人もいない。したがって能触と所触がなく、触れる者もいない。同様に、受ける者もなく、愛する者もなく、取る者もなく、有る者もなく、生まれる者もなく、老い死ぬ者もない。
原文:触を縁として受がある。また問うた。誰が受けるのか。仏は頗求那に告げられた。私は受ける者があるとは説かない。もし私が受ける者があると説くならば、あなたは誰が受けるのかと問うべきである。あなたは「何の因縁によって受があるのか」と問うべきである。私はこのように答えるべきである。触を縁として受がある。
受を縁として愛がある。また問うた。世尊、誰が愛するのか。仏は頗求那に告げられた。私は愛する者があるとは説かない。もし私が愛する者があると説くならば、あなたは誰が愛するのかと問うべきである。あなたは「何の因縁によって愛があるのか」と問うべきである。私はこのように答えるべきである。受を縁として愛がある。
釈:触を縁として受が生じる。頗求那がまた問うた。誰が受けるのですか。仏は頗求那に告げられた。私は受ける者があるとは説かない。もし私が受ける者があると説くならば、あなたは誰が受けるのかと問うべきである。あなたはこのように問うべきである。何の因縁によって受があるのか。私は答えるべきである。触があるがゆえに受が生じる、と。
受を縁として愛が生じる。頗求那がまた問うた。世尊、誰が貪愛するのですか。仏は頗求那に告げられた。私は貪愛する者があるとは説かない。もし私が貪愛する者があると説くならば、あなたは誰が貪愛するのかと問うべきである。あなたはこのように問うべきである。何の因縁によって貪愛が生じるのか。私は答えるべきである。受があるがゆえに貪愛がある、と。
原文:愛を縁として取がある。また問うた。世尊、誰が取るのか。仏は頗求那に告げられた。私は取る者があるとは説かない。もし私が取る者があると説くならば、あなたは誰が取るのかと問うべきである。あなたは「何の因縁によって取があるのか」と問うべきである。私は答えるべきである。愛を縁として取がある。
釈:貪愛を縁として取の行為が生じる。頗求那がまた問うた。世尊、誰が取るのですか。仏は頗求那に告げられた。私は取る者があるとは説かない。もし私が取る者があると説くならば、あなたは誰が取るのかと問うべきである。あなたはこのように問うべきである。何の因縁によって取が生じるのか。私は答えるべきである。貪愛のゆえに取が生じる、と。
原文:取を縁として有がある。また問うた。世尊、誰が有るのか。仏は頗求那に告げられた。私は有る者があるとは説かない。もし私が有る者があると説くならば、あなたは誰が有るのかと問うべきである。あなたは今「何の因縁によって有があるのか」と問うべきである。私は答えるべきである。取を縁として有がある。当来の有を招くことができる。触が生じる、これを有という。
釈:取を縁として三界の有が生じる。頗求那がまた問うた。世尊、誰が有るのですか。仏は頗求那に告げられた。私は有る者があるとは説かない。もし私が有る者があると説くならば、あなたは誰が有るのかと問うべきである。あなたは今このように問うべきである。何の因縁によって三界の有が現れるのか。私は答えるべきである。取の心行があるがゆえに三界の有がある。取は未来世の有を招来する。触が生じ出されれば、これを有という。
原文:六入処がある。六入処を縁として触がある。触を縁として受がある。受を縁として愛がある。愛を縁として取がある。取を縁として有がある。有を縁として生がある。生を縁として老病死憂悲悩苦がある。かくのごとく純大苦聚が集起する。すなわち六入処が滅すれば触は滅し、触が滅すれば受は滅し、受が滅すれば愛は滅し、愛が滅すれば取は滅し、取が滅すれば有は滅し、有が滅すれば生は滅し、生が滅すれば老病死憂悲悩苦は滅する。かくのごとく純大苦聚は滅する。
釈:六入処があるがゆえに触があり、六入処の因縁が触の生起を引き起こす。触の因縁が受を生じ、受を縁として愛があり、愛を縁として取があり、取を縁として有が生じ、有を縁として生命の出生があり、生命があれば老病死憂悲悩苦があり、このように純大苦が集起する。もし六入処が滅すれば触は滅し、触が滅すれば受は滅し、受が滅すれば愛は滅し、愛が滅すれば取は滅し、取が滅すれば有は滅し、有が滅すれば生は滅し、生が滅すれば老病死憂悲悩苦は滅し、純大苦聚は滅する。
十二因縁法においては、識を食とする者もなく、触れる者もなく、受ける者もなく、愛する者もなく、取る者もなく、有る者もなく、生まれる者もなく、老い病み死ぬ者もない。なぜならこれらすべての法は因縁によって生じたものであり、因縁によって生じた法にはすべて主宰がなく、主ではないからである。では、誰が識を食とするのか。誰が触れ、受け、愛し、取り、有り、生まれ、老い病み死ぬのか。能くする者はいない。これらはすべて浮雲のごとき仮象に過ぎず、過ぎ去って留まらず、絶えず移り変わり演変し、生滅変異して得ることができない。時が過ぎ境が遷れば、もはや触れることはなく、たとえ触れがあっても、当時のような受はなく、まして愛もなく、取着もない。しかしそれでもなお後世の有は避けられない。なぜなら別様の触、別様の受、愛、取があるからであり、これが変異である。
もし主宰者がいれば、これらの法は変異せず、常に一つの触、常に一つの受、常に一つの愛、常に一つの取、常に一つの有となり、生老病死はない。主宰者がなければ必ず生滅変異無常であり、恒常でなく、必ず識を食とする者もなく、触れる者、受ける者、愛する者、取る者、有る者、生まれる者、老い病み死ぬ者もいない。